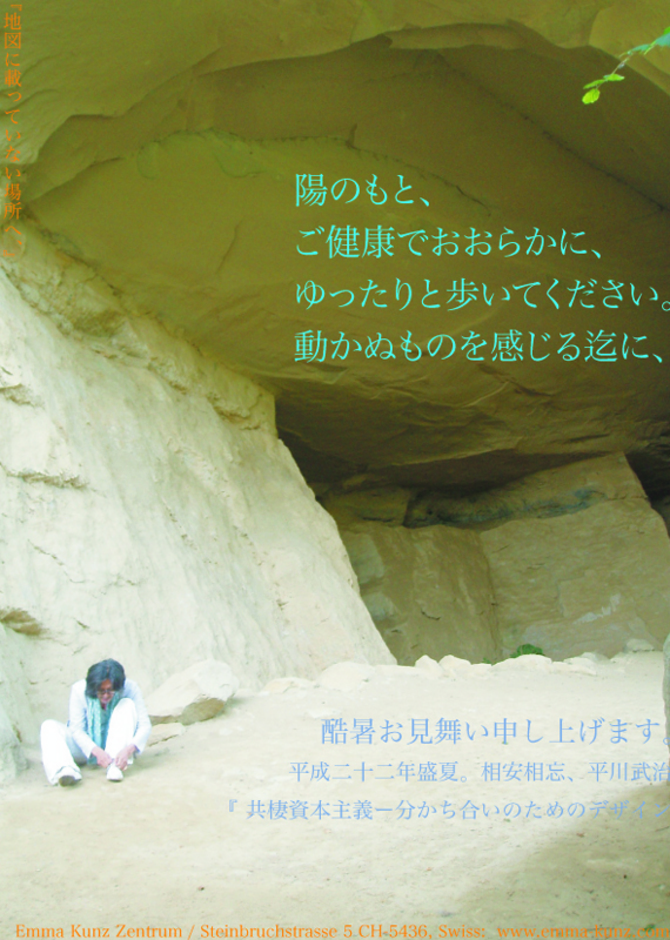« 2010年07月 | メイン | 2010年09月 »
2010年08月22日
『三伏の候、お見舞いを申し上げます。ご興味を持たれた方はこのサイトをご参照ください。』
2010年08月20日
三鷹天命反転住宅にて開かれる講演会のお知らせ。
先ず、僕自身に取ってとても嬉しいことなのですが、
「荒川修作+マドリンーギンズにより建てられた三鷹天命反転住宅」で行われる講演会へ呼んで頂きました。
小石祐介君始め、関係者のみなさま、ありがとうございます。
僕は20世紀も終わったころでしたか、ある年の正月、珍しく日本に居た時だったのです。
その数年前に、あの、荒川修作さんが現在このような事をなさっているという事をあるDVDで知り、
大いに関心を掻立てられていたので青春18切符を買っての旅へ、目指した所は『養老天命反転地』
一泊を岐阜で取り、翌日養老線で目的地へ向かうが、生憎この日は早朝からの大雪でした。
予想どうり、目的地は大雪の積雪の為、閉門。
大袈裟なことを考えると、この日の為に巴里から帰って来たのだ、だから、どうしても!!というこゝろの流行りが収まらず。柵を乗り越えての暴挙に出る。
このようなエピソードを持っている者にとっての今回のお呼びはとてもしあわせ感を感じるのです。
与えられたテーマは『にんげんをつくる』です。
ホモ-エクセレンスを考える?その為の環境としての『原始住居』
或いは、自然を始めとするあらゆるモノとの関係性の目覚め。
ご興味の在る方は是非!!
この機会にこの”化け物”にも関われ、語れるエピソードが持てます。
ファッションが好きな人たちももう、イメージにのみ頼っていては唯、ボケるだけ。
”エピソードを持つ”事によって語り合える迄の関係性が生まれる時代性です。
”身体拡張”ここには、モードが絡む一つの世界があります。
イメージに因りどこるだけでは”身体拡張”は語ることはできません。
8月22日の日曜日、13時より。
詳細はサイトをご参照ください。
http://www.architectural-body.com/mitaka/news/archives/2010/08/82126.html
帰国後間もないこの会です、時差ボケが酷いですが、感謝を素敵な時間にし皆さんと共有出来ればしあわせです。
ありがとう。
「生まれて半歳の平川武治が体験した終戦日とは、 その時の祖母は、母は?」
今日,8月15日になるといつもこの事を憶い、考えてしまうのです。
ここが、平川武治即ち僕が、自分の存在を認められるのか認められないのかのカオス。
今年の残暑の異常ですね、お見舞い申し上げます。
———へんな天候、へんな行為、へんな存在、へんな社会、へんなこゝろ使い、へんなヒューマニズム、へんなお洒落、へんな男、へんな女そして、へんな人間たちに気が付く事が日常的になってしまった最近の僕の周辺と環境。
日本人本来の美しさへのこゝろの在り方や想い方やその優美さの根源は何処ヘ忘れてしまったのだろうか?———
これは僕がここ、25年間の持ち得た生活環境が日本と外国とを約2ヶ月毎に行き来しているという中途半端な現実も手伝って見える僕の極めて個人的なる眼差しでしょう。
しかし、この僕の視点で,自分のボキャブラリーとして表現すると、帰って来る毎に同意される人たちが増えています。
これが今の僕たちの住んでる國の、へんな時代ですね。
みんな、”へんな”で括れてしまえる”へんな日本”の現実です。
”なぜ、へんなのか?”を考える前に、
「”へん”とはなにか?」って考えたり、思ったりした事がありますか?
『へん-偏』とは 偏っている事ですね。
ちょうわ、『調和』『バランス』が成されていないこと、
考えられていないこと、取れていないこと、無いことに尽きます。
そして、何のための、何との、『調和』かも考えられていないからでしょう。
『不自然さのさま』の事ですね。
そう、「自然」でない事なのです。
ここに、日本民族の”こゝろの在り方と置きどころ”が在ります。
僕たち、日本人は知らぬ間に、いつも、何かあれば理由無く、
それこそ、自然な思いつきと行為によって、
『自然』を中心軸としたバランスの取り方をし続けて来た民族なのです。
日本民族のこゝろのバランサーは『自然』なのです。
近くの池や川、海や山、雑木林、拾い上げる小石、道端の花、虫、鳥、
土そして、日と月。
生とし生きるものが自然。
天の、天地の恵みを享けて初めて育まれたものが『自然。』
その”自然の恵み”によって生かされて来た僕たちとご先祖さまたち。
この『自然』が変化した事、変化させられてしまった事によって、
僕たちの『こゝろのバランサー』が”へん”になってしまったのです。
戦後の、この65年間での現実的な価値は
『金』と『モノ』でしたね。
自然を愛おしむこゝろや他者を想い敬い合う
こゝろの在り方では無かった事は確かでしょう。
『貧しかったからでした。』が出発点だったからです。
だから、このような『自然』そのものが変化し、
僕たちのこゝろのバランサーを歪にしてしまった
『へんな』國になってしまったのです。
[たとえば、考えられる今様図式/
『金』+『モノ』+『驕り』=LUXURY=VANITY=KITSCH=『へんな』
これは全くのファッションの世界ですね。それが、いつの間にか、??????]
戦後も65年が経てば、
一つは、勤勉で真面目な僕たちはがんばって、
少しは、豊かさを味わい始めました。
もう一つは、
戦後に敗戦國だからという理由だけで押し付けられた
アメリカ合衆国という国家の”エゴ”が
そして、後ろでこの国家を動かしている集団が
又、その小間使いをさせられ,
番犬宜しく飼いならされてしまっている一部の日本人たちの、
彼らたちの「本心」が
どのようなレベルの
どんな目的の
誰たちの為の、
”エゴ”だったのかが解り始めて来ましたね。
解らない人は成熟してください。)
そんな、彼らたちの”エゴ”が唯一的、正論的に、
今後も続けば、
どのような環境になるか、どのような地球になってしまうのかも
そして、『自然』がどのように”へん”になるかも、
もう、僕たち自心で想像がつくようになりました。
これも戦後65年の彼らたちの”エゴ”のお陰でしょう。
学ばせて頂きました。
ありがとうございました。
だから、もう『アメリカ印の日本』を卒業して
『日本印の日本』を再生し始める時期に来てしまったのです。
もう、アメリカの表層事をいっぱい喋る事が恥ずかしい時代になりましたね。
それよりも僕たちが僕たちの国を想うこゝろを伝えあう事の方が
気概を感じる迄の時代が始まります。
そういう時代を迎えませんか?
みなさんも『へんな』ことに、
いっぱいの『へんな』事に気が付き始めたのですから。
『気が付けば、知ってしまえば、それに対して何が出来るか?
何をしなければならないか?』
”成熟する”という事は
この行為の為に学び、努力を持って
自心で誠意ある行為をする事ですね。
これ以上、
”へんな”ことが当たり前にならない前に
『へんな國』にならないうちに!
気概ある真こゝろを携えて
自心の成熟を。
ありがとう。
平成二十二年八月十五日/65回目の終戦記念日に。
ひらかわたけはる:
(この続きが在ります。ご興味の在る方は、サイト内をお探しください。)
2010年08月04日
『共棲資本主義』/参考資料:『分かち合いの為のデザイン』『分かち合い工学』を考える為に。平川武治版:
共棲資本主義/参考資料:2010年08月03日現在:
*J.アタリ/ "FRATERNITES"『反グローバリズム』/彩流社刊/ '09-6-20
*「分かち合い」の経済学 (岩波新書): 神野 直彦:
*『地域再生の経済学──豊かさを問い直す』(中公新書、2002年)
*『「希望の島」への改革──分権型社会をつくる』(NHK出版、2001年)
*『人間回復の経済学』(岩波新書、2002年)
*『教育再生の条件──経済学的考察』(岩波書店、2007年)
*[エコロジカル経済学の諸原理』/"Elements of Ecological Economics"
/ Routlede/2010-5-03/ISBN-1-:041547380 / ISBN-13:978-0415473811/Ralf Eriksson & Jan Otto Andersson
*宇沢 弘文教授/旭硝子財団-ブループラネット賞/’09年度受賞
http://www.af-info.or.jp/blueplanet/doc/lect/2009lect-j-uzawa.pdf
*セルジュ・ラトゥーシュ/"decroissance"(脱成長、縮退)理論の提唱者。
*セルジュ・ラトゥーシュの論文(日本語で読めるもの)
『経済成長なき社会発展は可能か?〈脱成長〉と〈ポスト開発〉経済学』(中野佳裕訳、作品社、2010年7月)
「生活水準」(『脱「開発」の時代――現代社会を解読するキーワード辞典』晶文社、1996年)
「収縮社会のために」(『世界』2004年2月号、岩波書店)
*サイト掲載/
「開発の自文化中心主義に抗して」
http://www.inclusivedemocracy.org/journal/vol3/vol3_no1_Latouche_degrowth.htm
『経済成長よ、さらば』/"decroissance"(脱成長、縮退)
http://www.diplo.jp/articles09/0908-4.html
http://www.diplo.jp/articles04/0411-4.html
"Would the West actually be happier with less? The World Downscaled", Le Monde diplomatique (December 2003).
http://www.hartford-hwp.com/archives/27/081.html
"Why Less Should Be So Much More: Degrowth Economics", Le Monde diplomatique (December 2004).
http://www.mindfully.org/Reform/2004/Degrowth-Economics-Latouche17nov04.htm
"Can democracy solve all problems?", The International Journal of Inclusive Democracy, Vol.1, No. 3 (May 2005).
http://www.inclusivedemocracy.org/journal/vol1/vol1_no3_latouche.htm
"How do we learn to want less? The globe downshifted", Le Monde diplomatique (January 2006).
http://mondediplo.com/2006/01/13degrowth?var_recherche=Serge+Latouche
"De-growth: an electoral stake?" The International Journal of Inclusive Democracy Vol. 3, No. 1 (January 2007).
http://www.inclusivedemocracy.org/journal/vol3/vol3_no1_Latouche_degrowth.htm
*ブログ『フィンランド発、持続可能な世界への転換』
http://www.ymparistojakehitys.fi/sustainable_societies.html
*オランダのエコ団体。
http://www.eco-efficiency-conf.org/content/2010.challenge.shtml
*ブログ『さて何処ヘ行きかう風が吹く』/
http://blogs.yahoo.co.jp/tessai2005/
*ブログ『東大環境学が解る-丸山真人』
http://www.sanshiro.ne.jp/activity/99/k02/interview/maruyama.htm
ハンスイムラーという経済学者の「経済学は自然をどうとらえてきたか」という本で彼がいっている言葉です。
結局、環境問題あるいは自然の危機というのは人間の生命の危機であるということなのですが、
「生態系の危機の本質的な内実は物証的な自然が危機にさらされているということではなく、
人間の本性が危険にさらされているということである」
*環境三四郎/
東大の環境を考える会:http://www.sanshiro.ne.jp/
*上野の住民のブログ:http://blogs.yahoo.co.jp/romanticnao/24933603.html
文責/平川武治:
初夏からの巴里にて、モードの街の新たな環境と強かさ。
プロローグ/東京が持っている温度差とは】
現在の東京はPOP=大衆消費社会の大きな固まりが泡沫化し始めた時代性。
この東京の現実はこの街、巴里とでもかなりの温度差がある、世界に類を見ない進化(?)の現実である。
誰でもが、何でも作り得られる時代のリアリテ(現実性)の消費社会化とPC及び、モバイル,デジタルカメラと
その周辺機器の高度なる発達とその利用の一般、日常化によって、”パーソナルメディア化”が始り、
現実をより、細分化し、バーチャルイメージを一般化しはじめたのが現在でしょう。
もう、『micro-POP』から『カオスPOP』迄の現実。
しかし、そのコンテンツは極めて保守的なるサンプリングでしかないのが現実。
唯、消費社会の構造そのものは、極度に発達し、あらゆるルールがカオス的な状況をもたらした。
例えば、バイヤーがデザイナーであり、デザイナーがバイヤーで或る現実性。
そして、彼らたちが持ち得たパーソナルメディアに依って、消費者が直接的にディレクション出来るまでの
大衆消費社会構造のバーチャル-リアリティな泡沫化。
そこでの新たな登場人物の行為は『バーチャルなイメージ』を頼りに『エピソード』を求めている輩たちの様。
イメージは綻び、どれもが埃を被った状態へ。
バーチャルな世界を頼りに、『エピソード』を求め合う彼らたちは何処を彷徨っているのだろう。
此処でも、終わりを知らぬ消費行動そのものが自発性の暴露である。
では、巴里の街は?】
保守化の進展或は倦怠はいつまで続く?
社会全体が閉塞感に浸りはじめる。この「窓」を開けるのは誰か?
早くも、より物質的な豊かさを生活に求め始めたイミグレーター(移民居住者)たちで構成された
新-大衆がこの閉塞感を打ち破れるのか?
―――彼らたちによる、新-中産階級の構造化が進む巴里。
消費文化そのものが消費財。―ミュージアムショップ的なるが全盛。
例えば、L.V.やエルメスなどのラグジュアリー系は自分たちのマークつき商品群を
嘗てのファッション、アクセサリーと靴バッグから時計、石ものジュエリーと香水とコスメから
陶器、オブジェ類や書籍に迄に延ばしはじめたラグジュアリィー-ミュージアムショップ系へと。
既に,消費そのものが大衆娯楽化し始めた。―アウトレット、eコマース、バーチャルマーケットのより、
一般化とリクレーション化。
そして、この街のファッション消費者たちも所謂、『新-大衆化』ヘの進展。
その一つは新たな大衆としてのイミグレーターたち、もう一つの新たな消費者たちとはジュニア層である。
彼等たちにとっては社会へのメッセージもまた,物質化し,消費財になリ、気概消費へも。
―ECO,BIO,オーガニック,コミュニティ等。
先ずは、登場人物を作り、その彼らたちへ『豊かさ』という味が付けられた”餌”を投げ込む仕掛けはいつの時代にも変わらない商業主義の世界の成せる技。
やはり、世界的不況】
この状況を被ってか、オムコレクションの今シーズンのバイヤーたちはおとなしい。
新たなデザイナーたちを買うまでには行かず、今までのデザイナーたちの並びを揃える程度の動きであった。
だから、サロンも今シーズンも比較的おとなしいシーズン。
『明日を楽しむため』に昨日のことで充分?な時代観。
明日を楽しむ為に、”昨日”の事ばかりでも、もうしょうがない閉塞感の時代に。
現在の巴里の消費の進展を見ている限り、嘗ての日本の消費社会の6、7年前の現実が今後の巴里。
新たな動きとしてのディフュージョンブーム到来?】
この街のモードも、所謂、「セカンダリーマーケット」を狙いはじめる。
その対称は、先程の『新-大衆』、イミグレーターたちのジュニアと中流階級者たちのジュニアたち。
従って、ターゲットとしては年齢層の低い、15~18歳が中心であろう。
彼女たちをMDした低価格帯の、彼女たちが着易い、着たくなるデザインとアイテム。
そして、デニムラインとのコーディネートファッションによるディフュージョンデザイナーブランド戦略が始る。
勿論、バッグやシューズも揃っています。
日本にも興ったことのあるプレタポルテデザイナーブランドのセカンドライン版のスタートだ。
新たに行われた「PARIS FASHION DAYS」/主催は巴里プレタポルテ協会。
この背景には当然乍ら、デザイナーモノの匂い&イメージ+低価格+生産背景=新たな消費者へのアプローチ。
という図式が見える。
此処で今回の参加デザイナーたちを見ると、生産背景がイタリーにあること。
従って、その工場が新たな戦略として巴里と組みこのセコンダリーマーケットを開拓しはじめる。
若しくは、アンヴァレリー.Aのように巴里の若手デザイナーであり、ニュークチュールもこなし、
プレタもやりそして、今回、このセコンダリーに参加という組は
或る意味でこの街のモードの優等生に選ばれたデザイナー。
なぜならば、優等生たちの幾度かのサンディカと伴に中国訪問の結果であるからだ。
今回の参加デザイナーはA.Fバンデボルスト(イタリー工場)/Ann v. Hash(中国生産)/
Vivian Westwood(イタリー工場)とイタリーからの3ブランドが巴里上陸。
解り易い構造であるがこれを新たなデザイナーブランドマーケットへ参入させる強引さが
この街にしてみれば新しく面白い。
これが今後、どの様に順調よく成熟したマーケットへ伸びるか、又は、サンディカが文句を言いはじめるか?
巴里のジャーナリストの友人は、「シブヤ系、109系と一緒よ!!」と自慢げに。
今までの”2階立て構造”が今後、新たに”3階立て構造”へ進化する可能性は読める。
又は、プレタポルテデザイナーたちの”2階建て構造”化にも繋がる。
この一番ボトムのデフュージョンラインが売れれば、自分たちのオリジナルラインのコレクションが
作れる迄の構造が確立されれば、これは此の国のモードの21世紀化でもあろう。
これも、或る意味では「H&M」効果と言える。
この街の「ファーストファッション」の誕生と共に、新たなイミグレーターたちを新-大衆とした
新しい消費構造がここに来てより、一般化したと言えるからだ。
theglobalherald.com/fashion-paris-fashion-days-enjoys.../5004/ 他、
変わらぬ中国への期待度】
この街のモード-ビジネスの強かさは今も尚変わらず、やはり伝統とクチュールに因り処って売り込んでいるだけである。
「君の國のファッションデザイナーたち、皆さん僕の街、PARISでショーをやってみませか?」というM.ディデエ-グランバックの挨拶ともセールスとも区別のつかない例の笑顔によって今回も、中国へ見事に上陸。
彼らたちはカレンダーを調節するだけ。これは無料。でもこの無料から有が生じるユダヤ人ビジネス。
後は、中国政府招待による、若手デザイナーたちを引き連れてのプロパガンダとデモストレーション。
巴里の新しさをチラ、チラさせる。そして、お金のあるデザイナーたちを呼び込み
彼らのショーをスケジュール内でセッティング。(その為のプレスは妹(2e Beaurou)が引き受ける構造。)
そして、幾度かの訪中の後にはフランス人若手デザイナーたちの為の生産工場と素材工場と言う
彼らたちの新たなビジネスの為に必要なバックグラウンドの関係性が誕生。
これは、ある意味で未だ”植民地政策”と変わりない構造。
しかし、嘗ての日本もこの手によって現在の様な規模と進化のファッションビジネスが誕生し,
その約10年後には現在の様なファッション大国に成長したのである。
だから,この中国という大国もその実効果はやはり、インデペンデントな独自のビジネス展開迄には
10年は掛る可能性があろうか?
その間に此の国の”モードのショーケース”はより、確実に一つ一つ、自分たちのステージの上に引き寄せ、
今世紀の今後も、「クチュール致上主義」を展開してゆくのだ。
その展開の一つが先の『セコンダリーマーケット開発』でもあろう。
デザイナーブランドのイメージングさえ確りしていれば、
これからは「グローバリズム」という恰好のレッテルがあるから、
さあ、もう『MADE IN FRANCE』でなくとも『MADEIN CHINA』で良い時代性とレンジのレシピ。
そして、中国の後はインドを経て『AFRICA』か??
新たな『夢』の為に】
新学期が始った日本のファッション学校で生徒たちと接して、改めて驚き考えさせられた事があった。
それは彼らたちにはもうファッションに対する『夢』願望が少なくなってしまった世代である事を知ったのだ。
では夢でなく何かと言えば、もっとビジネス的、若しくは現実的なる『儲け』と『カッコ良さ』と
その『バニィティーさ』それに、好きなファッションが出来て、勤められるという迄のレベルのに変わったようだ。
それだけ、ファッションが彼ら世代にとっては当たり前のものになったのだろう。
巴里におけるコレクションを見ても、トレンドはその後すぐにファーストファッションのショップで
又、アウトレットでもおかしくない、eコマースでも楽しめ、サイトのオークションでも、もっと安く手に入るという幾つかのメニューまでの現実性と遊戯性。
そして、コレクションは『過去を物語るボキャブラリィー』がそのデザインの殆ど。
新しさは『過去時計』を良く見ることから生まれる迄の保守とその閉塞感。
そこで、僕はこの『夢』が消え始めたファッションの世界に『夢』を再びと念い考えた結果が、
『テクノロジー』である。(この詳細は前回に書いたものです。)
その僕なりの眼差し『テクノロジー』をベースに今シーズンのオム-コレクションを見ると
それなりの読み方が見え始めた。
コレクション-デザイナーに見た『テクノロジー』】
RAD HOURANI/昨年のイエール参加の新人デザイナー。アントワープ系。
コンセプトは然程、新しく無くなった所謂『ガンダム系』
フスナー使いに依っての幾通りに着こなすことが出来るタイプ。
素材はレザー中心に黒のみそして、今シーズンのトレンドとしての『ユニセックス』モノ。
頭のいいデザイナであろう。仕上がりの縫製テクニックが良い。
このデザイナーに営業的にやり手のお金大好きパートナーが付いたからこのようなスタートが出来た。
彼女も嘗ては、ヨウジの売り子だった女性。
巴里の前に、N.Y.で発表させるという手の内、強かである。
RICK OWENS/一生懸命若作りで今の時代の先端を引っぱているデザイナー。
或る意味で、嘗ての映画、『マッドーマックス』のテクノロジー版。
多分、一番先を勝手に走っているデザイナであろう。
ROMAIN KREMER/最近、此処数シーズンの彼の世界は共感出来る或る種の新しいさを感じる唯一人のデザイナー。
スポーツとプレタをミックスして彼が作る世界の独創性はノスタルジックな未来趣味がベース。
今シーズンも好奇心溢れるコレクションを。
いつも人とは違う事をしたい若手の独り。
CdG HP/このデザイナーもいつも人と違うことばかりを成し遂げて来た人。
この現実の彼女のパワーと好奇心と努力が此の国に彼女の立場を作り得た。
今回も、プリントの世界で日本の『プリント-テクノロジー』をオンパレード。
何をプリントしたかと言うと、『骸骨』。
これを意味ありげなコンセプトを作ってのジャーナリストへ発信。
変わらぬ、トレンドのフレーム内での”人がやらぬことを!”が続くメディア受け狙いなシーズン。
しかし、この凄さが、却って、此の国のデザイナーたちに受けるし、
これが新たなトレンドを呼ぶ迄のエゴであるからその発想と努力とその現実のテクノロジーの凄さには、
今の外国人デザイナーたちで列ぶ者が居ないのも現実。
”異端と異系”を継続することのみが僕たち、外国人デザイナーたちの自分自身を確立する為の最短方法であることを
この街へ来て20年足らずで学んだ唯一のデザイナー。
此処にも、彼女が信頼するしかない、日本の縫製技術は勿論、素材と素材加工技術と
プリント技術の強さをいつもコレクションで魅せてくれる唯一のデザイナー。
例えば、今回のプリントコレクションは、
スクリーンプリント(顔料プリント)、インクジェットプリント、転写プリント
そして、柄の種類も踏まえ、生地の組み合わせは
スクリーンプリント=19種類、インクジェット、転写プリント=8種類に分けられます。
また、骸骨(スカル)柄の種類数
表地=12種、裏地=4種。 そして、表地の種類、柄の組み合わせで全部で25通り。
お見事な算術で構成されたコレクションである。
RAF SIMONS/僕が好きな所は「RAF-IZM」的なる世界観を変わらず続けていることである。
或る種のフーチャーティックさと男の身勝手なロマンティックさそして、
男の役割としての”らしさ”や”臭さ”を求めているその彼の純なおとこ心に引かれるからである。
此処にも彼の眼の凄さと狙い目としても「日本の新素材」がある。
これからの新しさとしての『新-機械主義』的な動きは彼がいち早く感じ取っているのであろう。
此処で今後、彼のクリエーションでプラスされるべき事は、『勇気』である。
もっと、思い切った事を!!を望んでしまう。
此処に上げた幾人かのデザイナーたち、古手、中堅、若手たちそして新人、彼等が率先して、
『アルティザン-テクノロジー』と『サイエンステクノロジー』の新たなバランス観で”21世紀モード”の
クリエーションを考える事は今後の若いモードを目指す若者たちへ『夢』そのものを与える事であろう。
ここに、新たな『新-機械主義』的な動きが始る。
そして、予告的な発想では、次のファムコレクションにはこの「プリントモノ」がトレンドを生むであろう。
文責/平川武治:ST.-CLOUDにて: